被扶養者の認定基準は、次の資料を参照ください。
組合員の配偶者、子、父母などで、主として組合員の収入によって生計を維持している者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。
被扶養者として認められる者は、主として組合員の収入によって生計を維持していて、原則的に日本国内に住所を有している(日本国内に生活の基礎があると認められる)次の者です。
(5. 6.については、組合員と同一世帯に属する者が該当します)
| (注) | 日本国内に住所を有しない者でも、海外留学をする学生や海外に赴任する組合員に同行する者などについては、例外として認められます。 |
|---|
18歳以上60歳未満の者(学生、病気やケガ等により就労能力を失っている者を除く)は、通常、稼働能力があるものと考えられる場合が多いので、このような場合には、扶養事実及び扶養しなければならない事情を具体的に調査確認し判断します。
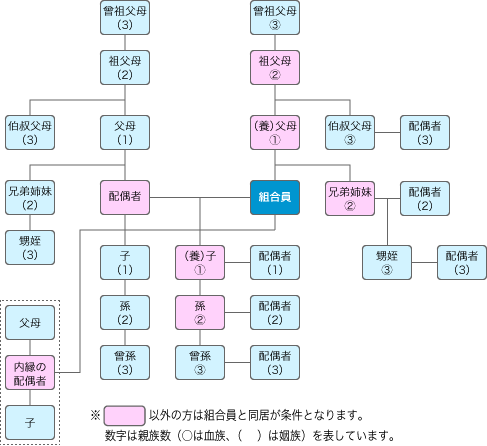
新たに被扶養者の要件を備える者が生じた場合、その旨を「被扶養者申告書」により所属所を経由して共済組合に届け出(5日以内)なければなりません。なお、30日を過ぎて届出がなされた場合、申出日からの認定となり、扶養事実の生じた日から認定日までの間に生じた病気等についての給付も行われないことになりますので、遅れないように「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。
組合員の被扶養者が、就職等により被扶養者資格を喪失したときは、速やかに「被扶養者申告書」を所属所を経由して共済組合に提出してください。資格喪失後、保険医療機関等で受診があった場合は共済組合から返還請求(保険者負担等)を受ける場合がありますので十分注意してください。
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により、国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の認定及び取消(注)と同時に年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」を共済組合に提出してください。
| (注) | 取消の場合で届出が必要な事由
|
|---|
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。
被扶養者が、扶養の認定を受けている期間のうち、「一時的に就労していたことがある」という方はいませんか。
扶養認定基準額(年額130万円)未満の収入であったため気に留めていなかったところ、当該期間が社会保険の適用を受けていたというケースがあります。
また、社会保険の適用を受けていたことは承知していたものの、それが短期間であったために共済組合への手続きを怠っていたというケースもあります。
就職したことにより、社会保険の適用を受けることになった場合は、共済組合に速やかに扶養取消の手続きをしていただかなくてはなりません。その後、退職したことにより再び扶養認定の要件を満たせば、扶養認定(被扶養配偶者においては第3号被保険者届)の手続きを行っていただくことになります。
この一連の正規の手続きが遅れると次のようなことが起こり得ますのでご注意ください。
扶養の取消は社会保険資格取得時点までさかのぼります。
しかし、認定はその事実発生の日から30日以内に届出がされない場合、その届出があった日から認定することになります。
したがって、社会保険の資格喪失の日から30日以内に扶養認定の届出がされなかった場合は、共済組合では、社会保険の資格喪失の日から届出の日までの間の給付を行うことができないため、その間にかかった医療費を返還していただくことになります。
共済組合の組合員は、組合員となった日から同時に国民年金の第2号被保険者となり、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は第3号被保険者となります。
しかしながら、配偶者が就職し、厚生年金に加入した場合、その期間は配偶者自身が第2号被保険者となります。その後、会社等を退職(第2号被保険者の資格を喪失)し、再び共済組合の扶養認定を受ける場合、共済組合を経由して国民年金第3号被保険者に関する届出をしなければなりません。
この手続きを怠ると、国民年金の加入記録上、第2号被保険者の資格を喪失した状態のままとなりますので、1日でも社会保険の適用があれば、必ず速やかに届出 を行ってください。